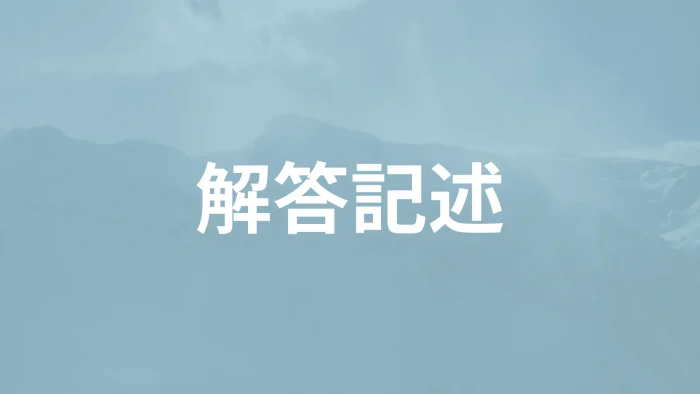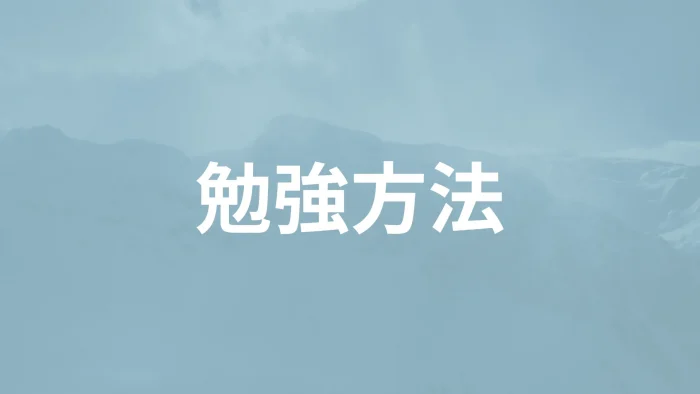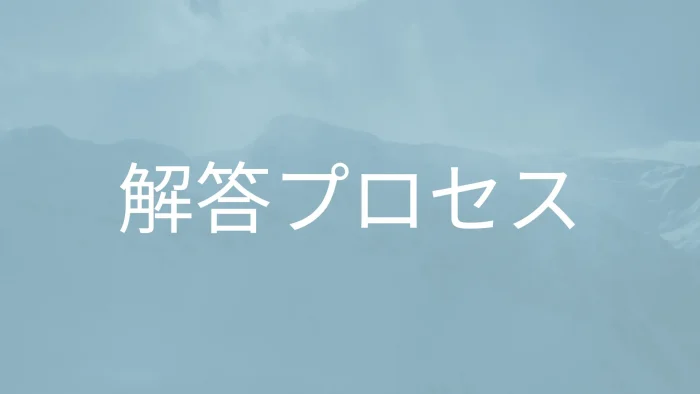「仕事の都合や、地方在住なので予備校に通うのが難しく、独学しか選択肢がない」
私は、独学で1次試験を2回、2次試験を2回の合計3年をかけて、中小企業診断士試験に合格しました。
独学ではまわりの受験生が見えないので不安でした。
今回は、以下3つの不安を克服する方法をご紹介します。
- 結果が出るか不安
- スケジュールに関する不安
- 勉強に対する不安

独学で不安を抱えている方は、ぜひご覧ください。
2次試験で結果が出るのか不安
他の受験生との力の差はどれほどなのか?
「独学だと他の受験生のレベルが分からないので不安」
「ふぞろい」の合格、A、Bと自分の解答を見比べればだいたいの位置はわかります。
合格、Aレベルの解答を安定して書けるのが合格水準です。
合格・A解答のキーワードでなく、解答の構造に注目してください。
合格、Aレベルの解答は重要なキーワードを含みやすい構造で、論理的に書かれています。
論点・切り口が抜けてないかを意識してください。
キーワードだけ意識してても、拾えた拾えてないを繰り返すだけでなかなか前に進めないからです。
合格できるのか?
「ふぞろい」の合格、Aレベルの解答を安定して書けるのが合格水準です。
ポイントは以下の3つです。
- 設問の注文すべてに対応できている
- 解答が構造化されている
- 事例4の基礎問題が解ける
この3点から逆算して、合格までの道筋や課題を整理してください。
順番に詳しく説明していきます。
①設問の注文全てに対応できている
設問の注文を見落としていると評価が低くなります。
なぜなら、論点やキーワードが外れるからです。
設問の注文に対応できているかは、キーワードの余り具合で検証してください。
たまたま拾ったキーワードではなく、設問対応の結果拾ったキーワードで評価してください。
拾えなかったキーワードと設問の論点・切り口を対応付けて、「どのように設問を解釈すればキーワードを落とさなかったのか」を検証、ルール化して次に活かしてください。
②解答が構造化されている
構造化されている解答は、与件から拾ったキーワードが含まれていて、論理的に記述されています。
「ふぞろい」の合格、A、解答はこの解答の構造化がしっかりしてます。
解答の構造化は、「文章の型」を身につけることで比較的短時間でマスターすることが可能です。
「文章の型」はこちらの記事をご覧ください。
「文章の型」を使った解答文章の書き方とトレーニング方法を解説します。「文章の型」を身につけると論理的な文章を短時間で書けるようにます。比較的短時間で身につくので、ぜひお試しください。
③事例4の基礎問題が解ける
事例4が重要だとよく聞きますが、
前提として他の事例で安定して点が取れることを忘れないでください。
応用問題を初見で解けるレベルでないと事例4で差を付けられませんが、応用問題は解けなくても合格できます。
また、基本問題(経営分析や管理会計など)の配点は意外と大きめです。
応用問題を捨てて基礎問題を確実にとるスタイルもありだと思います。
他の事例演習に時間を使うか、事例4の応用問題(イケカコとか)に時間を使うか、あなたのスタイルに合わせて選択してください。
応用問題を無理に解かなければ、試験本番でも基本問題に対して多めに時間を使えるのも大きいです(もちろん、応用問題の部分点は取りにいってください)。
私は、応用問題を捨てて基礎問題を確実に取るスタイルでしたので、基礎問題が中心の「集中特訓 財務会計の 計算問題集」を繰り返しました。
2次試験のスケジュールに関する不安
このまま続けていて間に合うのか?
独学だと学習スケジュールを誰も組んでくれないから、自分で組むしかありません。
でも、「全体の見通しも立たないのに、どうやって学習スケジュールを立てるのか」
私もかなり悩みました。
全体の見通しを立てるために、習熟度別に集中して取り組むことを整理しました。
| 導入期 | 成長期 | 直前期 |
| 2次試験(過去問)に慣れる | 課題の洗い出しと克服 | 弱点補強 |
| 解答プロセスの整理 | 解答プロセスの見直し | タイムマネジメント |
| 必要知識の整理 | 不足知識の補充 | 必要知識の再整理 |
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
2次試験の勉強の進め方をご紹介します。 また、学習スケジュールの立て方と、おすすめのテキストもご紹介します。
何から勉強すればいい?
科目別の視点
事例2と事例3で設問への対応力がついてから事例1に挑戦するのがいいと思います。
事例1は「設問の意図」が捉えづらいので後回しです。
各科目の特徴をまとめました。
- 事例1:設問の意図が捉えづらい
- 事例2:全体のストーリー、設問間の関連性・一貫性を意識
- 事例3:素直。キーワード整理を意識
事例4は、毎日仕事帰りにコツコツやっていくのがオススメです。
アウトプット(計算)が中心なのと、試験本番では4科目目なので疲れた頭で挑まなくてはならないからです。
解答プロセスの視点
「設問解釈」から勉強を進めてください。
これができれば、あとは自然とついてきます。
解答プロセスは以下の順番です。
- 設問解釈:何を聞かれているのかを整理する
- 与件整理:与件文から必要な情報を拾い上げ、整理する
- 解答記述:採点者が理解できるように文章を書く
解答プロセスの具体的な内容はこちらの記事をご覧ください。
解答プロセスの具体的な手順と、解答プロセス見直しのポイントをお伝えします。2次試験対策は「解答プロセス」を育てることです。各ステップの課題をひとつひとつクリアすることが、合格へのカギです。
2次試験の勉強法に対する不安
実践している勉強方法は正しいのか?
「予備校で教えてもらう解法とかすごそう」
予備校の合格率は20〜30%と高くはありません(全体の合格率は20%前後)。
独学でも十分合格を狙える試験です。
以下のような勉強方法がおすすめです。
- 解答プロセスを整理する
- 過去問で失敗した理由と対策を考える
- 対策を解答プロセスに組み込む
ポイントは、反省点(対策)をプロセスに落とし込むことです。
試験本番は育てた解答プロセスで粛々と設問に対応するだけです。
ぜひ、あなたの解答プロセスを育ててください。
使っているテキストや問題集はこれで良いのか?
あなたにあったものを選んで使えばいいです。
なぜなら、使うテキストで合格率に顕著な差があると聞いたことはありませんから。
定番だからと合っていないものに時間を使って無駄にするのが、一番もったいない。
おすすめのテキストは、こちらの記事で紹介しています。
2次試験の勉強の進め方をご紹介します。 また、学習スケジュールの立て方と、おすすめのテキストもご紹介します。
試験でのタイムマネジメント
試験当日は大崩れを防ぐために、以下の工夫をしました。
- 時間までに次の工程に進む(時間いっぱいはNG)
- 10分のバッファを設けて、心に余裕を作る
各工程を時間いっぱい使っていたら、一つの工程が時間オーバーになると全体が間に合わなくなるので、多少雑でも次の工程に移りましょう。
また、「解答プロセスが固まってない」「時間をかけても合格水準の解答が書けない」うちに、タイムマネジメントを気にしても無駄です。
先に、この2つをクリアしてください。
まとめ
- 「ふぞろい」の合格、A、Bと自分の解答を見比べればだいたいの位置はわかる
- ゴールから逆算する
- 解答プロセスを育てる
- 顕著に合格率の高い予備校やテキストはないから、あなたに合ったものがいい
それでも不安な方は、連絡ください。相談にのります。
関連記事
次のステップ
解答プロセスの具体的な手順と、解答プロセス見直しのポイントをお伝えします。2次試験対策は「解答プロセス」を育てることです。各ステップの課題をひとつひとつクリアすることが、合格へのカギです。